|
みなさんは、「シックハウス」という言葉、耳にしたことがありますよね。
ここ数年、新聞やテレビ、住宅情報誌などで頻繁に見かける言葉です。
シックハウスとは、簡単に言えば、住宅内に放出された化学物質の影響で様々な健康被害を生じさせる現象のことですが、実はまだ謎だらけなのです。
シックハウス “Sick House” =病んでいる家= という言葉は造語であり、もともと英語で “Sick Building Syndrome” として知られてきた症候群なのです。シックハウス症候群は先進国を中心に、世界中に広がっていますが、その背景には住宅のつくりそのものの変化があるようです。
特に日本の場合、その変化は驚くほど急速に進みました。30年くらい前までの日本の住宅は、ほとんどが木造で、日本の四季の気候に対応して木材は適度に伸び縮みして、良くも悪くも家にすき間をもたらし、自然の風が家の内外を自由に行き来できました。
ところが、次第に鉄筋コンクリ-トで造られた住宅やマンションが増え始め、家の気密が格段に良くなってしまったのです。そして、木造住宅においても、アルミサッシが普及したり、壁や天井の材料に合板や石膏ボ-ドが使われるようになったりと、建物が密封されるようになってきました。
一方で、家の内外装や家具などに使用される材料も低コスト、大量生産、大量消費という時代の流れとともに多様化し、様々な塗料や化学物質が使われるようになってきました。
建材や家具などに用いられる化学物質の中には、ごく微量ずつではあるものの、揮発して空気中に出て行くものがあります。ところが、昔と違って気密化された家の中では、空気中の化学物質は外に出て行くことができずに、滞留してしまうのです。
こうした化学物質によって引き起こされるのが「シックハウス症候群」なのです。
気密化された住宅が、化学物質を含む建材で作られており、そこに住む人も家の気密性を意識せずに昔の住宅の感覚で生活する。(換気をしない。)このことが、近年シックハウス症候群が社会問題化している背景でしょう。
シックハウス症候群は、化学物質過敏症の一種として位置づけられています。
化学物質過敏症は、一度に多くの化学物質を体内に吸収したり、少量でも長時間さらされたりすることによって起こる、過剰反応とされています。
また、化学物質に対する耐性(許容量)は、人によって違うとされています。これをバケツと水にたとえれば、人の化学物質に対する耐性がバケツであり、そこに水にたとえた化学物質が貯まってきて、バケツからあふれ出したときに、化学物質過敏症が発症するのです。人により、持っているバケツの大きさも違いますから、同じ量の化学物質にさらされても、症状が出る人と出ない人がいるということになるのですね。
では、具体的になにが原因でどのような症状が出るのでしょう。主な事例と関連原因を、国民生活センタ-に寄せられた相談内容で見てみましょう。
ケ-ス①
新築の戸建住宅へ入居直後から妻は湿疹が出て、病院で診てもらった。自分も全身がかゆい。以前住んでいた家に戻ったところ、症状は軽くなってきた。建材などの使用に法律上の規制があるかどうか知りたい。
(60歳代 男性)
ケ-ス②
3年前に建築された高気密性の建売住宅に入居後、夫婦ともに具合が悪くなった。頭痛、めまいがしてとてもいられない。ホルムアルデヒド(指針値0.08ppm)を測ってもらったら、0.23ppmだった。 (30歳代 女性)
ケ-ス③
健康に良い材料を使うといわれ、1年半前に家を新築した。秋頃より食欲不振、吐き気、だるさを感じるようになり、シックハウスのことを知った。保健所でホルムアルデヒドを測定してもらったところ、0.14ppmであった。業者に除去対策を相談したら、原因を特定しないとできないといわれた。 (40歳代 女性)
ケ-ス④
床暖房のフロ-リングの工事終了後に、床暖房のスイッチを入れたところ、ものすごい刺激臭がした。その後、自宅にいると、妻の具合が悪く、医師はシックハウスだという。トルエン濃度を調べると、基準値の10倍もあり、事業者は工事をやり直すというが、やり直して妻の症状が良くなるのだろうか。(50歳代 男性)
ケ-ス⑤
子供の入学前に学習机を購入した。配送してもらった翌日から、子供に目が赤くなるなどの症状が出始めた。眼科へ通院しているが一向に良くならない。(10歳未満 女児)
現時点では、シックハウス症候群はもちろん、化学物質過敏症についても、原因と症状の因果関係について、明確な回答が得られるというわけではありません。しかし、様々な症状に苦しみながら、原因と考えられる物質を遠ざけることにより、健康生活を取り戻そうとしている方が少なからずいることも事実なのです。そのため、厚生労働省もこれらの化学物質についての濃度の基準を設けるなどの作業を進めていますし、建築業界においても、住まいを提供するものの責任として、より健康な住宅を提供する為に努力するべきなのです。
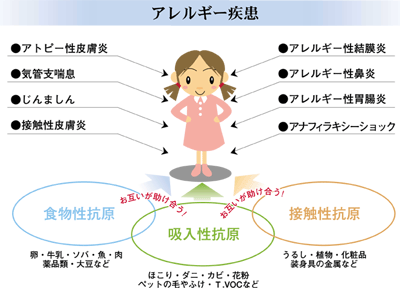
|

